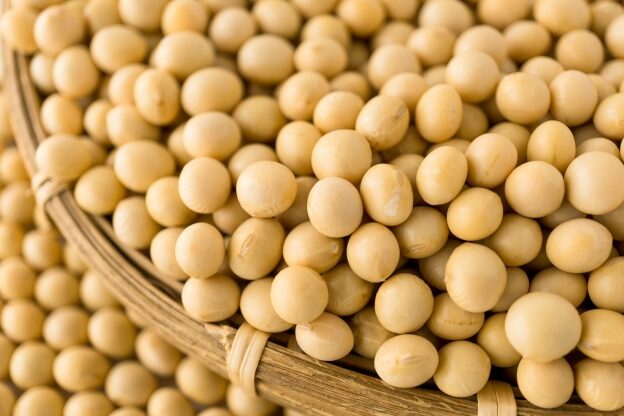豆はたんぱく質をはじめとする栄養が豊富な食材ですが、その摂取量には注意が必要です。
きな粉は、記事などで「豆腐の5倍以上のたんぱく質が含まれている」と報じられることがあります。100gあたりのたんぱく質量を比較すると、きな粉が約37gであるのに対し、木綿豆腐は約6.6g、絹ごし豆腐は約4.9gと、確かに5倍以上です。しかし、実際に一度に食べる量を考えると、話は変わってきます。きな粉は一袋100g程度ですが、一度に食べるのは小分け袋の20gほどです。一方、豆腐は一丁350~400gあり、一度の食事で100gどころか、200g以上食べることも珍しくありません。きな粉20gに含まれるたんぱく質量は、絹ごし豆腐150gとほぼ同じであり、グラムあたりの比較だけでは実態を正確に把握することは難しいのです。
高野豆腐も同様に、「木綿豆腐の7倍のたんぱく質が含まれている」と報じられることがあります。100gあたりで比較すると、高野豆腐には50.5gのたんぱく質が含まれているため、木綿豆腐の約6.6gと比べると7倍以上です。しかし、高野豆腐は1切れが約16gと小さく、50gのたんぱく質を摂取するには6切れ以上食べなければなりません。さらに、高野豆腐はだし汁でもどして食べることが一般的ですが、水で戻すと100gあたりのたんぱく質は10.7gに減ります。そのため、調理後の状態では、豆腐とのたんぱく質の差はわずかだと言えるでしょう。
注意すべきは、きな粉や高野豆腐が乾燥食品であるという点です。「日本食品標準成分表」は100gあたりの栄養素を示しているため、水分の少ない食品は相対的に栄養素が多く表示されます。例えば、きな粉の水分は3~6gであるのに対し、豆腐は85g以上が水分です。乾燥状態の高野豆腐は水分が7.2gですが、水煮にすると79.6gに増えます。つまり、「栄養素が豊富」と報じられる食品の多くは、水分が少ない状態で比較されているケースがほとんどです。もちろん、海藻類や大豆製品が栄養豊富なことに変わりはありませんが、一つの食材にこだわる必要はなく、様々な食品をバランス良く摂取することが大切です。